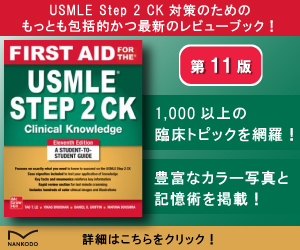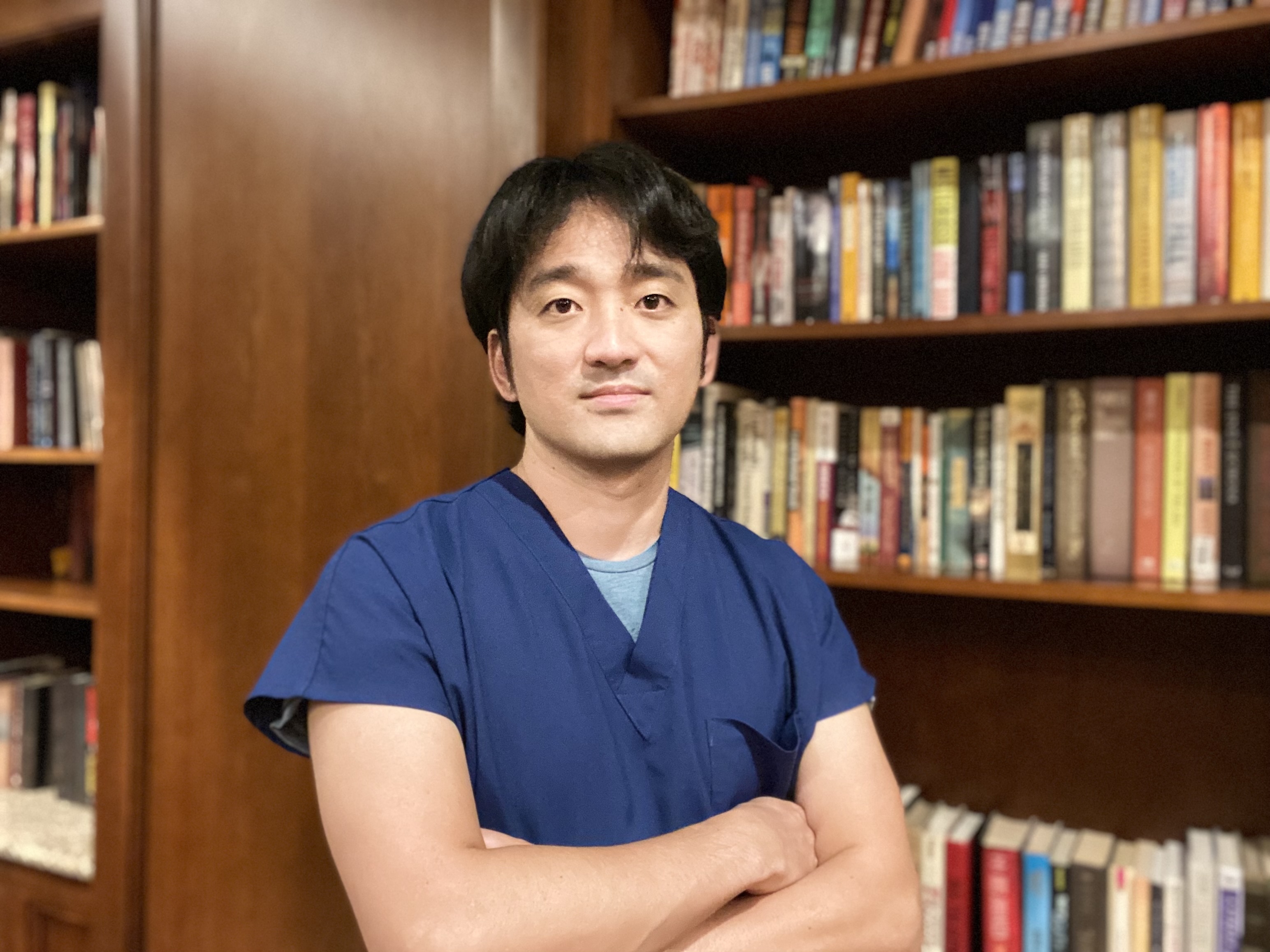【コラム】アメリカへの研究留学で得たこと、学んだこと

《著者》
溝口 恵美子 氏
久留米大学医学部免疫学講座教授、
ブラウン大学医学部分子微生物免疫学講座客員教授
はじめに
はじめまして!
久留米大学医学部免疫学講座で基礎研究をしている医師の溝口恵美子です。
私は、約24年間、アメリカで研究生活を送りました。この経験をもとに、皆さんに少しでも役立つ情報をお届けできればと思い、このサイトにコラムを執筆することになりました。生い立ちや、渡米に至った詳しい経緯、留学中のエピソードなどはYouTubeシリーズ「JrSr~未来の医師への贈りもの101回」でもお話ししていますので、是非ご覧ください。
留学したきっかけ
大学卒業後、母校の久留米大学内科で臨床研修を行い、2年目から同大免疫学講座の大学院に進学しました。指導教授の横山三男先生(Professor Michel Mitsuo Yokoyama)は、日本人には珍しくアメリカ市民権を持ち、ハーバード大学やハワイ大学、イリノイ大学などで四半世紀にわたって教鞭をとられた高名な免疫学者でした。「ストレスと免疫」「においと免疫」などユニークで最先端の発想を持ち、常に「今やらずにいつやる」が口ぐせ。 若手のやる気を引き出す指導をされる先生でした。
この横山先生との出会いが、海外で研究するキャリアパスを考えるきっかけとなり、アメリカへの留学が夢ではなく、現実的な選択肢になりました。そして、大学院3年目の夏、ボストンのマサチューセッツ総合病院(通称、MGH)へ留学するチャンスに恵まれたとき、「念ずれば叶う!」という言葉を実感しました。留学は決して特別なものではありません。皆さんも自分から動けば、必ずチャンスは巡ってきます。
留学前の英語力について
私は、中学1年生から英語を学び始め、リーディングや文法は得意でしたが、発音は完全な日本人英語。大学時代はJIMSA(日本国際医学ESS学生連盟)に所属し、英語を話す機会もありましたが、「アメリカで“railroad station”とか“blue”が通じなくて苦労した」という先生の話を聞いても、当時はあまり実感が湧きませんでした。
しかし、実際に留学生活が始まると、自分のRとLの発音が正しくできていないことや、リスニングの難しさを痛感しました。また「トイレ」「ピンセット」「ピペット」などの和製英語が全く通じないことにショックを受けつつ、「こう言えば伝わるのか!」という発見の連続でした。
英語を上達させるには、できるだけネイティブの方と話す機会を持ち、アクセントやリズムを意識することが重要です。私は今でも「ELSA Speak」というアプリを活用し、毎日20分の練習を続けています。また、医学英語の習得も不可欠です。医学部在学中からmedical termsに親しみ、しっかり勉強しておくことが、研究留学の成功につながると思います。
アメリカでの基礎研究生活
私は留学中、臨床活動は一切行わずに、MGHの病理学講座(免疫病理部門)で10年、内科学講座(消化器内科部門)で14年にわたり基礎研究に専念しました。この二つの講座では、研究の進め方や指導方針に大きな違いがあり、研究室の雰囲気や方針を事前に把握することの重要性を実感しました。これから海外留学を考える皆さんも、自分の研究スタイルに合った環境を選ぶことをお勧めします。
病理学講座で学んだこと:仮説思考と研究の本質
病理学講座では、部門長だったAtul K. Bhan教授から、“Thinking process”と “Hypothesis-driven research”の重要性を徹底的に叩き込まれました。毎週行われるBhan 先生とのミーティングはアットホームな雰囲気でしたが、焦点は常に「仮説に基づいた実験結果をどう解釈するか」に置かれていました。決してボスの意見を押し付けられることなく、自由な発想のもとのびのびと研究に取り組むことができました。
この期間に、「なぜ?どうして?」と疑問を持つ習慣が身につき、徐々に論理的な思考が鍛えられていきました。特に、免疫組織染色法の理論を習得しながら技術を磨いた最初の1年間は、なかなか理想とするような結果が出せず、試行錯誤の連続でした。しかし、ボスは根気強く私の成長を待ち続けてくれ、条件の最適化を重ねた結果、世界で初めて炎症性腸疾患を自然発症するマウスモデルの樹立に成功しました。この経験を通じて「継続して努力すれば、必ず結果はついてくる」という信念が私の中に根付きました。
また、MGH以外のハーバード大学附属病院の著名な研究者とも共同研究を行う機会を得て、研究者としての自覚や、英語でのコミュニケーション能力を養うことができました。
消化器内科部門での挑戦:臨床と基礎の融合
その後、消化器内科部門では、より臨床に即したTranslational research(橋渡し研究)に携わりました。最初の5年間は、当時の部門長であり、まさに“飛ぶ鳥を落とす勢い”だったDaniel K. Podolsky教授のもとで研究を進めました。
この部門には、臨床経験を持つ医師がClinical fellowやResearch fellowとして一定期間研究に専念するプログラムがあり、実臨床と密接に結びついた研究が活発におこなわれていました。ここでは、病理学講座にいたとき以上に英語でのプレゼンテーションの機会が増え、質疑応答を通して論理的に意見を伝えるスキルが身についていきました。
2006年からは、“Principal Investigator(P.I.)”として独立した研究室を持ちました。しかし、研究費の獲得競争やラボ運営のプレッシャーは想像以上に厳しく、何度も押しつぶされそうになりました。それでも、「Positive-thinkingの姿勢を持ち続けること」で困難を乗り越え、研究を継続することができました。
多様な価値観とカルチャーショック
この部門にはアメリカ・カナダ・南米・ヨーロッパ・アジア諸国から多国籍の研究者が集まっており、異なる文化・価値観に触れることで、柔軟な思考力やグローバルな対応力が鍛えられました。特に印象的だったのは、「休暇の考え方」と「仕事に対する評価の違い」です。欧米では、普段しっかりと仕事をしていれば2~3週間連続の休暇を取るのが一般的で、「遅くまで残っている人」はむしろ「仕事の効率が悪い人」と評価されることが多かったです。日本の「疲れ切るまで働いて、やっと数日の休みを取る」という文化とは対照的でした。
このような環境に身を置いたことで、自然と柔軟な思考や危機管理能力が養われ、現在の久留米大学での国際医学交流の仕事にも大いに役立っています。また、アメリカ留学中、共に切磋琢磨した仲間とのネットワークは、今でも私の人生を豊かに彩ってくれています。
支えてくれたパートナーへ感謝を込めて
最後に、33年間にわたり、公私ともに私を支え続けてくれている夫・溝口充志の存在なしに、私の研究者生活は語れません。彼の寛大さと忍耐強さ(!)には、心から感謝しています。
(了)
この記事の著者

溝口 恵美子 氏
久留米大学医学部免疫学講座教授、
ブラウン大学医学部分子微生物免疫学講座客員教授
<略歴>
1990年 久留米大学医学部医学科卒業後、同大旧第1内科入局
1991年 久留米大学免疫学講座で大学院生として研究開始
1992年 米国ハーバード大学医学部附属、マサチューセッツ総合病院病理学講座留学
1994年 久留米大学医学院医学研究科修了(医学博士)
1997年 ハーバード大学医学部病理学講座 Instructor
2006年 ハーバード大学医学部内科学講座 Assistant Professor
2016年 久留米大学免疫学講座 准教授
2019年 米国ブラウン大学医学部 客員教授
2022年 久留米大学免疫学講座 教授(国際医学交流担当)
現在に至る ※2025年4月時点