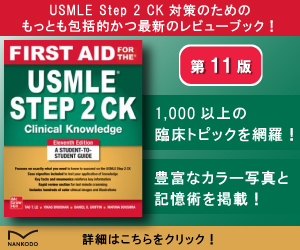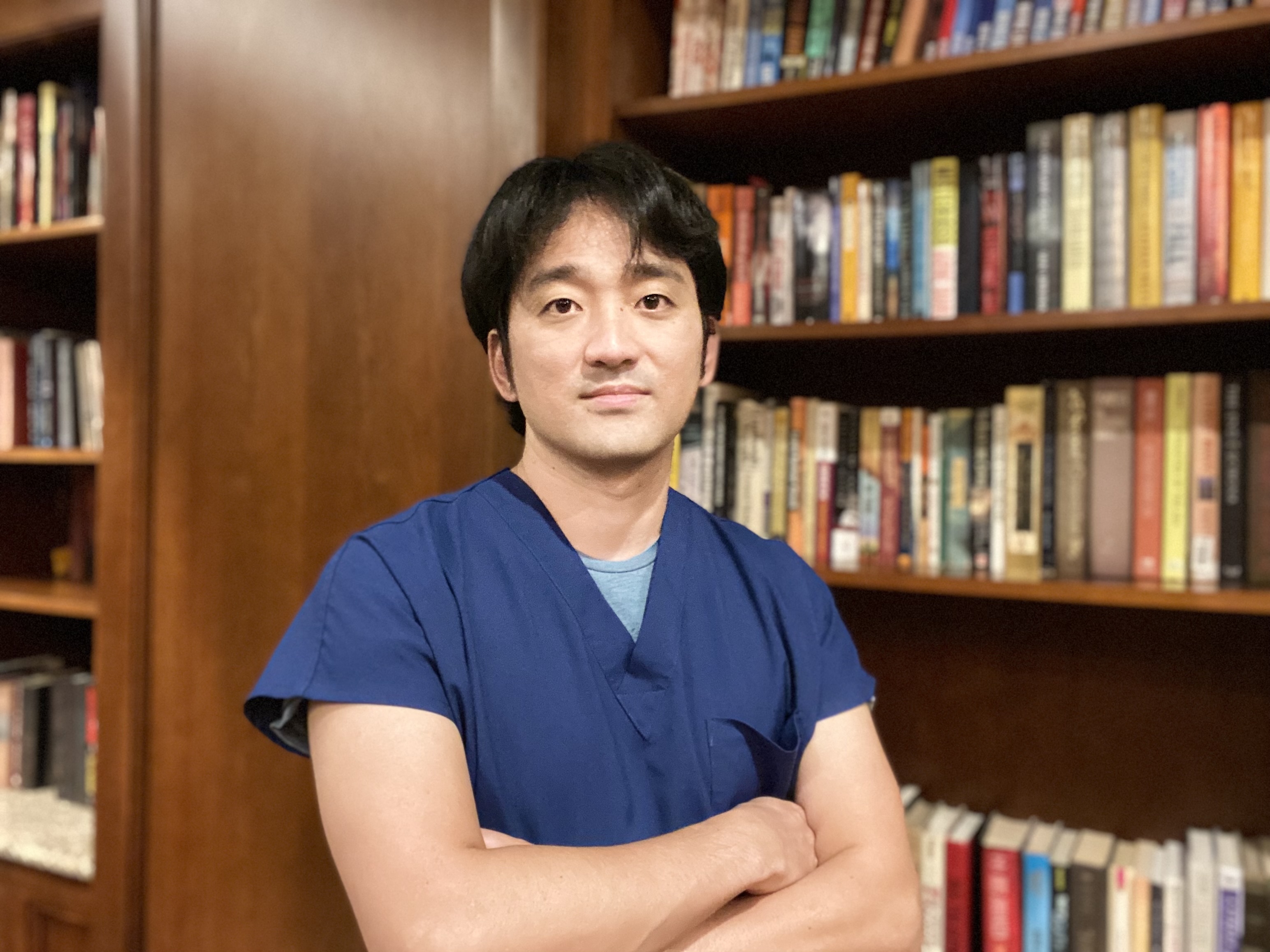現役医学生が山田悠史先生に聞く―医師の海外留学とキャリア<前編>
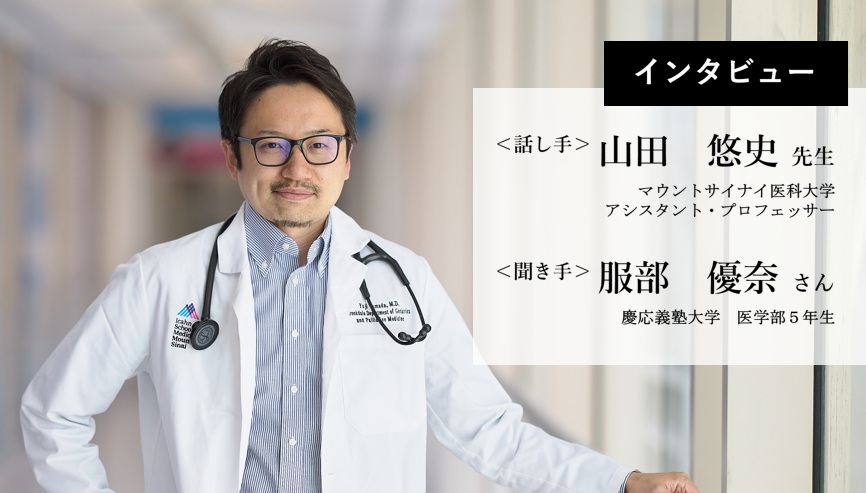
米国・マウントサイナイ大学で勤務され、SNSやメディアで様々な情報発信も続けられている山田悠史先生に、医師の海外留学について、現役の医学生が本当に知りたいことを聞きました。
服部 優奈 さん
慶応義塾大学医学部5年生
予防医学および総合内科領域への関心をきっかけに、日米の医療の違いや臨床留学に興味を持つ。現在は各種委員会活動や臨床研究等に取り組み、知見を広めている。2026年に、Hawaiiにて Hospital Medicine・General Medicine・Family Medicine を中心とした5週間の臨床実習を予定。
ーー留学のきっかけを教えてください。
最初にアメリカに渡ったのは医師7年目の頃です。もともと学生時代から留学には興味があって、大学1年生のときに「First Aid for the USMLE」と「六法全書」の2冊を購入し、弁護士になるかアメリカで医師になるか、どちらかに進もうと考えていました。日本の医学部に所属していれば医師になること自体は当然のように実現できると思っていたので、それに加えて何か挑戦したいと思ったのです。結果としては、法律にはまったく興味が持てなかったため、USMLEの道を選びました。
明確に留学への火がついたのは、大学6年生の時に参加したアメリカでの留学プログラムです。そこでfamily medicineという、日本ではあまり馴染みのない診療科を見て感動し、ここで学びたいと思いました。
しかし、日本で初期研修が始まると、目の前の仕事が忙しく、かつ楽しくて、留学のことはしばらく忘れていました。それでも、医師1~4年目はできることがどんどん増えていたけれど、5年目に差しかかるくらいの頃から、同じ症例を繰り返しているように感じはじめ、医師としての成長が止まったように思えました。そこで、一回医師を辞めてみようと思い立ち、バックパックで世界一周に出ました。
半年でお金が尽きて帰ってきましたが(笑)、そこで二つのことを再確認しました。一つは、やっぱり医師が好きであるということ。もう一つは、海外で医師として働きたいという自身の夢です。ヨーロッパを周遊する中で、現地の医師たちは複数の言語を話し、海外で自由に働き、活躍の場が広いということに衝撃を受けました。一方、自分はすごく狭い世界で生きていると痛感したのです。そこから、アメリカで医師になるという学生の頃からの夢をもう一度真剣に考え、英語力ゼロから2年間で準備をして、最終的に医師7年目の時に渡米した、というのが留学までの経緯です。ずいぶん遠回りの話になりましたが、人生とは紆余曲折で、本当にいろいろあるものなのだと感じています。
ーー実際に留学を決意してから渡米までの2年間、どんな準備をされたのですか?
渡米までの期間は本当に大変でしたが、一番大きかったのはやっぱり英語です。私は岐阜県出身で、大学までは日本から出たこともほとんどなく、ヨーロッパを半年間周遊したといってもほとんどジェスチャーで乗り切ったようなもので(笑)、まともに英語は話せませんでした。
留学を決意した頃はすでに30歳に差し掛かっていました。当時、AI英会話などはなく、オンライン英会話を毎日必ず1回は受けるようにし、英会話の時間を確保しました。そして、自分の目や耳に触れるものを全部英語にしました。例えば、テレビはあえてCNNしか映らないようにし、またiPhoneに入っていた音楽を全て削除し、代わりにNHKワールドの英語放送や、The New England Journal of MedicineのAudio Summaryだけを入れました。唯一残した日本語の音源は、心雑音のCDだけという状況です(笑)。プライベートの時間を削り、通勤時間や、食事や入浴の時間など、とにかく隙間時間を活用し、徹底的に英語漬けの状況を作り出しました。
その時点でUSMLEのStep1とStep2 CKはすでに持っていたので、残っていたのは当時まだあったStep2 CS。これは英会話力があれば何とかなる試験だったので、準備を始めてから2年目で受験し、合格。これで渡米の準備が整いました。今振り返ると、学生時代から少しずつでもUSMLEに手をつけていたおかげで、一から始める人よりは楽だったと思います。遠回りはしましたが、昔やっていたことは無駄じゃなかったなと、その時に強く感じました。
当時自分に言い聞かせていたのは「何かを得るには、何かを捨てなければいけない」ということ。友人や病棟からの飲み会の誘いもほとんど断りました。犠牲は多かったかもしれませんが、後悔はありません。
ーーご自身の努力に加えて、周囲のサポートや後押しはありましたか?
ありました。まず、自分を支えてくれる環境を意識的に選びました。留学前の2年間は、アメリカ帰りの指導医がいる病院で勤務し、空き時間に英語でのプレゼン練習や患者プレゼンをさせてもらうなど、日常的にトレーニングの機会を得られました。さらに、その病院では留学志望者が複数おり、長期不在となることを許容してもらえる体制が整っていたため、4か月ほどアメリカでオブザーバーシップを経験することもできました。これは普通の勤務医では難しいことです。仲間同士で励まし合えたのも大きな支えでした。
もうひとつ大きかったのは、自分から動いて人と出会いに行ったことです。留学準備のセミナーや交流会に積極的に参加し、その中で強く背中を押してくださる先輩医師と出会えたことが、進路を大きく変えるきっかけになりました。出会いは待つものではなく、自ら掴みに行くものだと実感しました。
ーー留学して実際にどんな経験をされましたか?
面接対策としては、200個の想定質問とその回答を作り、丸暗記して臨みました。鏡の前で練習し、笑顔でスラスラと話せるようになっていたため、面接の場ではあたかも英語が流暢なように見えていたかと思います。しかしいざ働き始めると、2年間準備してきたつもりでも言語においては大きな壁を感じました。特に最初の半年間は、独特の略語や用語、文化的背景が分からず苦労しました。これは英語が得意な人でも避けられない課題で、同じく途中から来た帰国子女の仲間も口を揃えて「最初の数か月が一番つらい」と言っていました。同期と愚痴を言い合い、励まし合いながら乗り越えた時期です。
慣れない環境で再び研修医の一番下の立場から始めることになるので、ペーパーワークやクレーム対応などの雑務も多く、医療が少し嫌いになりかけたこともありました。特に冬のニューヨークは寒さも相まって精神的に落ち込みやすかったですが、半年を過ぎて暖かくなる頃には英語にも業務にも慣れ、前向きに取り組めるようになりました。
医学そのものは国が違っても同じであるというのが根本にあり、それが支えにもなりました。ただ、米国では徹底した分業がなされていることが印象的でした。日本よりも医師の担当範囲が狭く、役割が明確に分かれている点は強く感じた部分です。
ーー英語力と臨床能力、どちらも大事だと思いますが、臨床能力は日本である程度積んでから行くべきでしょうか?それとも早いタイミングで留学した方がいいでしょうか?
基本的には、自分が行こうと思ったタイミングが正解です。早すぎるとか遅すぎるということはありません。ただ、歳を重ねるほど結婚や出産、親の病気など、制約が増えてくるので、早い方が可能性は高いと言えるかもしれません。私は医師7年目で、すでに日本での臨床経験を積んでいる状態での渡米だったので、米国での同期よりも採血や腹水穿刺などの手技は確実でしたし、疾患の基礎知識や身体診察の経験も十分にある状況でした。そのおかげで、現地では周りから頼られることも多く、初めての環境でもある程度自信を持って臨めました。逆に若いうちに行く人は、日本での臨床経験は少なくても時間をかけて現地で鍛えられるので、どちらにもメリットがあると言えます。
結論としては、臨床経験を積んでから行くと安心感や有利な面はありますが、だからといって遅い方が良いとは思いません。大切なのは、自分が挑戦したいと思ったタイミングで行動することだと思います。
Interviewee

山田 悠史(やまだ ゆうじ)氏
マウントサイナイ医科大学 アシスタント・プロフェッサー
2008年慶応義塾大学医学部卒業。東京医科歯科大学病院(現:東京科学大学病院)、川崎市立川崎病院、練馬光が丘病院を経て、2015年よりマウントサイナイベスイスラエル病院で内科レジデントとして勤務。2020年にマウントサイナイ医科大学病院で老年医学フェロー。2022年より現職。