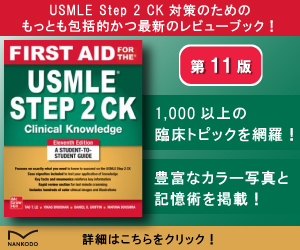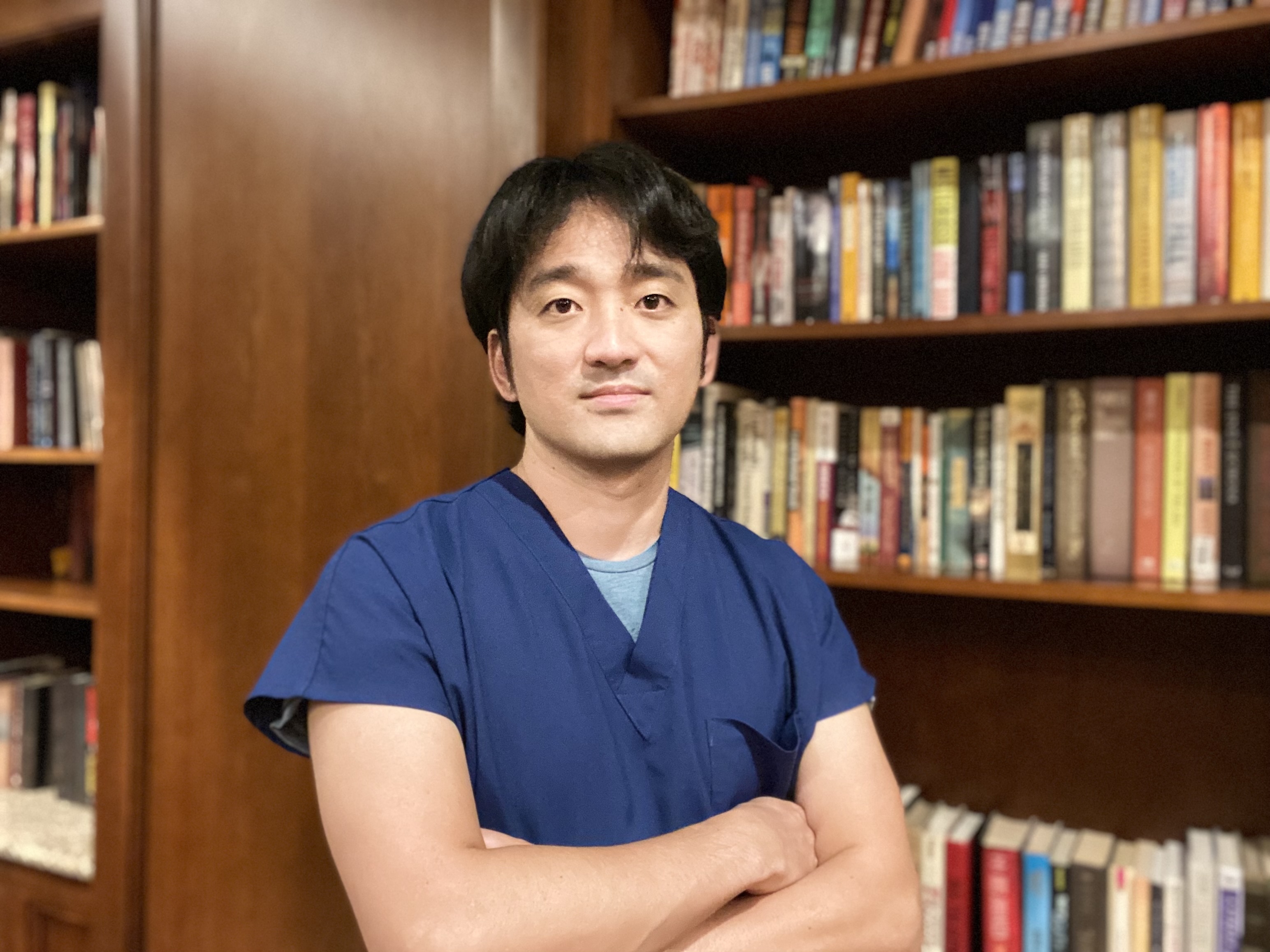世界と競い、臨床能力を高めよう ― 竹村洋典先生に聞く海外留学
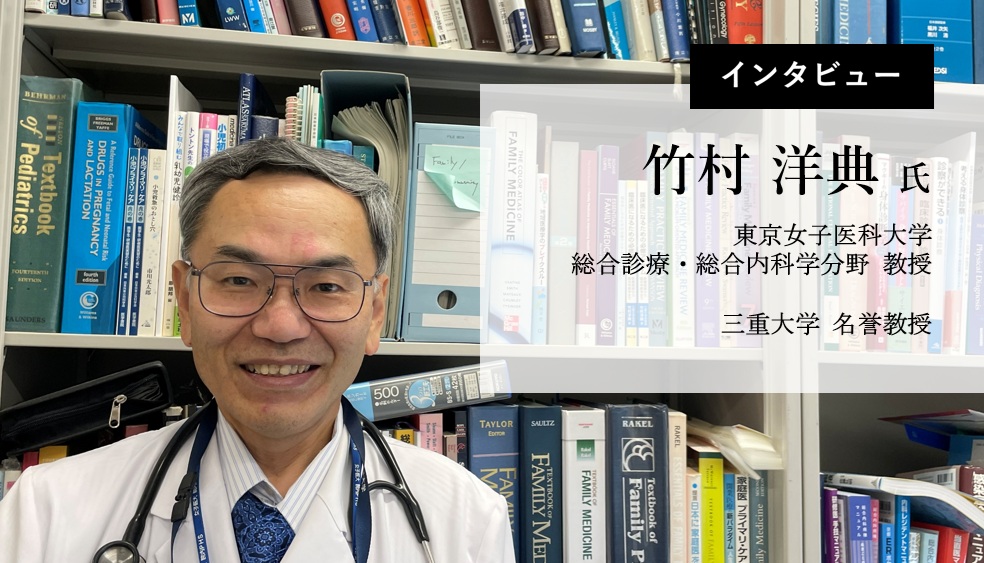
米国で総合診療・家庭医療を学び、現在は東京女子医科大学で総合診療の実践と教育に取り組まれる竹村洋典先生に、ご自身の海外留学の経験や、これから留学を志す医学生・医師へのメッセージを伺いました。
ーー学生時代に海外留学を目指したきっかけを教えてください。
私は帰国子女ではなく、卒業後に臨床留学をするまでは、海外に行った経験はほとんどありませんでした。学生時代、防衛医科大学では米軍関係者と接する機会があり、それに刺激を受けたことも影響したかもしれませんが、もともと知的好奇心が高く、常に新しいことに挑戦する性格であることが大きいと思います。そのような性格だからか、米国で一緒に働いていた同僚からは「西部開拓時代のパイオニアのようだね」言われたことがしばしばあります(笑)。
ーー留学までの勉強はどのようにされていましたか?
学生時代、英語は主にNHKの「基礎英語」で勉強していました。英会話の機会を得るために、横田基地の医師を訪ねたりもしました。USMLEは、Step 1を大学4年生、Step 2は6年生のときに受験し、それぞれ合格しています。医学部の授業でも、テクニカルタームはすべて英語で頭に入れるようにし、難解な疾患名も英語で覚えました。一方で、日本の医師国家試験対策にはあまり力を入れておらず、最低限の勉強しかしていなかったかもしれません。
教科書は、各分野で国際的に最も権威のある書籍を選んで読んでいました。ハーパー(Harper’s Illustrated Biochemistry、生化学)、ガイトン(Guyton & Hall Textbook of Medical Physiology、生理学)、ロビンス(Robbins, Cotran & Kumar Pathologic Basis of Disease、病理学)、グッドマン・ギルマン(Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics、薬理学)、ハリソン(Harrison’s Principles of Internal Medicine、内科学)、セシル(Goldman-Cecil Medicine、内科学)、ネルソン(Nelson Textbook of Pediatrics、小児科学)、ウィリアムズ(Williams Obstetrics、産科学)、カプラン(Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry、精神科学)などです。いずれも分厚い大著です。防衛医大では手当が支給されるので、書籍の購入費にあてていました。また、診断学のサパイラ(Sapira’s Art & Science of Bedside Diagnosis ※絶版)やレイケル(Textbook of Family Medicine)、スワンソン(Swanson’s Family Medicine Review)といった書籍にも深い感銘を受けたのを覚えています。
ーー米国での臨床の経験について教えてください。
コネは一切なかったので、米国にある約400のレジデンシープログラムに申請用紙を依頼しました。返事が戻ってきた80のプログラムに応募し、そのうち13のプログラムで面接に進みました。プログラムによっては、選考過程でレジデントとの夕食会がもうけられることも少なくなかったのですが、積極性や協調性など、そこでのふるまいが性格面の評価につながっていたことを、実際にレジデントになってから知りました。
英語での臨床は、最初はとても苦労しました。特に小さい子どもが相手だと「腹部に痛みがある」ということを正確な表現で伝えてくれるとは限りませんし、「膝を曲げてください」などの簡単な指示も、最初は英語でどのように言えば良いのか、周りに聞きながら覚えるしかありませんでした。はじめの数ヵ月間は、頭の中で翻訳をしながら会話することになり、頭が熱くなる感覚をおぼえました。しかしだんだんと、英語で考え、英語で伝えられるようになり、不思議なことに発音も次第にアメリカ人のようになっていくのがわかっていきました。
ーー総合診療や家庭医療における米国と日本との違いはどのように感じられましたか。
日本の総合診療専門研修プログラムも近年はかなり充実してきましたが、私が留学していた当時は、やはり米国の総合診療における研修プログラムの包括性には圧倒されました。家庭医として、分娩介助も230例ほど対応し、娩出された直後の新生児のケアも自ら担当しました。包皮切除術や精管結紮術など、日本ではあまり出会わない手術も数多く経験しました。
米国では「患者中心の医療」が強く意識されており、当時はすべての研修プログラムに行動科学の教員が配置されていました。自分が診察する様子をビデオで撮影され、その映像をもとに行動科学の観点からフィードバックを受けるのです。「Disease」ではなく「Illness」を診る、という姿勢は、非常に参考になりました。
多職種との連携の密度が強いというのも特長だと思います。看護師、薬剤師や栄養士、リハビリはもちろん、ソーシャルワーカーなどとも密に連携し、多角的、総合的に患者さんのケアに携わりました。
世界中の医師たちと競い臨床能力を高める
ーー医師にとって海外留学は必要でしょうか?
医師としての臨床能力を高めるためには、日本だけにとどまるのではなく、世界の医療の現場に立ち、世界中の医師たちと競い合いながら腕を磨くことはとても重要です。
開発の進む薬剤の情報等に比べると、総合診療などのプライマリケアの技能は、まだ日本に十分には導入されていない海外の知見が数多くありました。一方で、海外に出てみることで、日本の医療や生活の良さを再発見することもまた多くあります。留学を通じて世界と対等につながり、学ぶだけでなく、得た知見や技術を日本に持ち帰ったり、反対に日本の医療を海外に広めていったりすることには、大いに意義があります。
また、医学の世界で英語によるコミュニケーションが取れると、世界中にたくさんの交友関係が出来上がります。一度できた世界中の仲間たちとのつながりは今でも続いています。家族ぐるみの交流がある友人も多いです。グローバルな視点をもった医師とのネットワークはきっと大きな財産となると思います。
ーー海外留学を目指す医師に向けてメッセージをお願いします。
近年、海外に行く日本人医師が減っていると聞きます。一度海外の臨床現場を経験すると、世界が狭く感じられ、先進国でも途上国でも、どんな医師とも対等に意見交換することができます。これからの時代、バウンダリーを越え、様々な国の医師に勝負を挑み、また、心が通い合う関係が構築され、世界を股にかけられる日本の医師が増えてほしいと願っています。
もし、少しでも海外留学に興味があるのなら、夢をあきらめずに挑戦し、何年かかっても達成してください。情熱を持ち続けましょう。
(了)
Interviewee
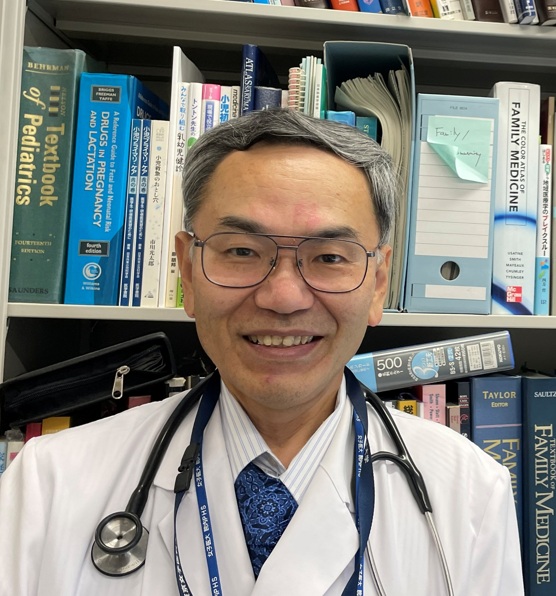
竹村 洋典(たけむら ようすけ)氏
東京女子医科大学総合診療・総合内科学分野 教授
三重大学 名誉教授
1988年防衛医科大学卒業。1991年から米国テネシー大学医学部家庭医療学科レジデント。1995年から米国ウォルター・リード研究所、タイ王国プラモンクットラオ病院にて熱帯医学研修フェロー。2001年より三重大学総合診療科。WONCA(国際家庭医学会)の学術誌Asia Pacific Family Medicine誌の編集長をつとめた。2021年より現職。